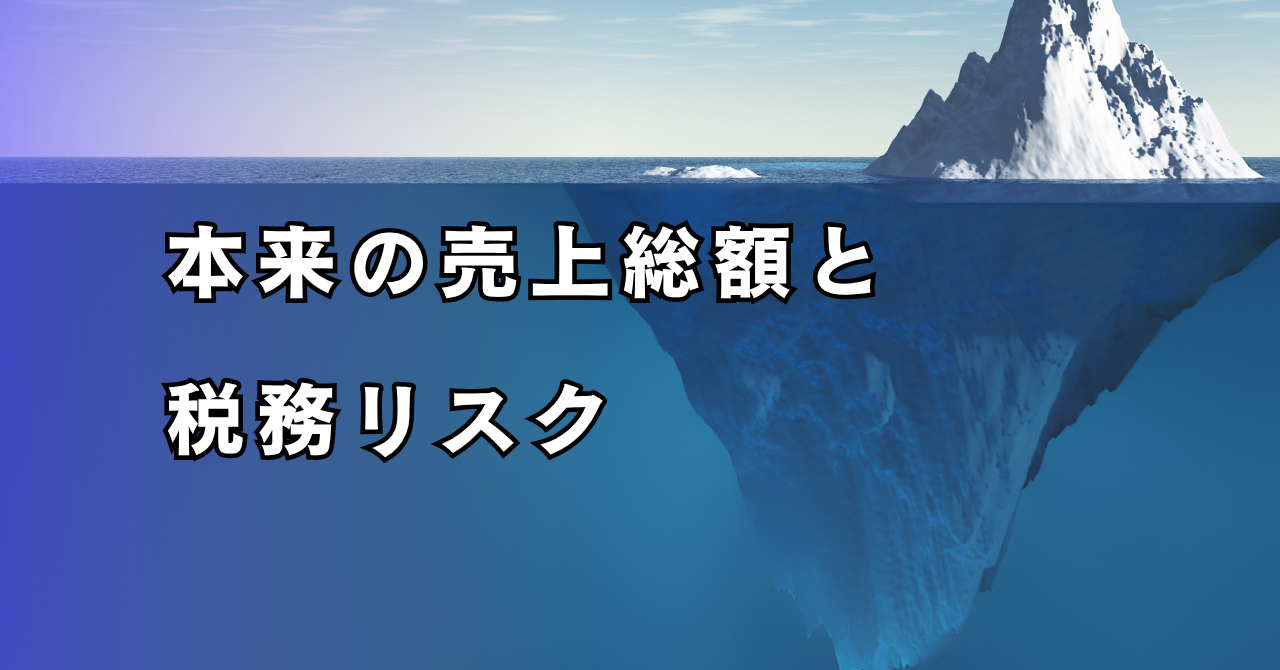取引先からの入金の際、材料費などが相殺され、その差引後の金額で売上計上をしていませんか?その経理処理は、税務上のリスクをはらんでいます。
特に消費税の申告では、意図せず納税額を誤り、将来的に追徴課税されることにもなりかねません。
この記事では、なぜ相殺してからの売上計上が危険なのか、そしてあなたをリスクから守る正しい経理処理の方法を分かりやすく解説します。
相殺による売上計上が、なぜ原則NGなのか?
まず、売上と経費を相殺した差引後の金額だけで売上計上する方法(純額計上)は、原則として認められていません。
なぜなら、会計には「総額主義の原則」という、取引の全体像を正確に把握するための基本的なルールがあるからです。
そして重要なのは、消費税の納税義務の判定や納税額の計算は、この会計ルールに則って正しく計算された「売上高(総額)」を基に行われるという点です。
つまり、「利益は変わらないから」と会計の基本ルールとは違う処理をしてしまうと、意図せず売上の総額が本来より少ない数字で記録されてしまい、それがそのまま消費税計算のスタートラインになることで、結果として税務上の大きな問題に直結します。
これが、会計上の問題が税務上の大きなリスクに発展する理由です。
例えば、110,000円(うち消費税10,000円)の工事を請け負い、その取引先から仕入れた材料費22,000円(うち消費税2,000円)が相殺されて、88,000円が振り込まれたケースを考えてみましょう。
- 誤った処理(純額計上): 売上 88,000円
- 正しい処理(総額計上): 売上 110,000円 / 仕入高(材料費) 22,000円
一見すると利益は同じに見えますが、会計上の正しい売上高が歪められてしまうこと、それこそが、後々大きな問題を引き起こすことになるのです。
【補足】振込手数料の扱いは?
ちなみに、実務上よくある「振込手数料」が売上から差し引かれて入金されるケースでは、その手数料を「売上値引」として処理することが認められています。
これはあくまで例外的な扱いであり、今回のテーマである材料費などの経費を相殺することとは性質が異なる、と覚えておきましょう。
相殺が招く「売上計上」の誤りが、納税義務と2割特例の適用に与える影響
入金時に相殺された金額をそのまま売上計上することで最も怖いのが、消費税に関する重要な判定を誤ってしまうリスクです。
まず一つ目は、消費税の納税義務そのものの判定です。
消費税を納める義務がある「課税事業者」になるかどうかは、原則として2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定されます。
相殺後の金額で売上計上していると、この重要な判定を間違えてしまうのです。
仮に、あなたの事業の2年前の売上が、本当は1,200万円あったとします。
しかし、取引先から仕入れた材料費などの経費250万円が相殺されていたため、帳簿上の売上を950万円として計上していました。
この場合、「売上は1,000万円以下だから、消費税の納税義務はない(免税事業者だ)」と判断してしまうかもしれません。
しかし、税務上の正しい判定は、相殺前の1,200万円で行われます。つまり、本来「課税事業者」であり、消費税の申告・納税が必要だったのです。
そして二つ目は、インボイス登録をした方が特に注意すべき「2割特例」の適用判定です。
「インボイス登録をしたから、どのみち納税義務がある。それなら基準期間の売上は関係ない」…そう考えるのは早計です。
なぜなら、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている事業者は、2割特例を適用することができないからです。
もし、相殺後の売上計上で基準期間の売上高を1,000万円以下だと誤って判断してしまうと、本来は使えないはずの2割特例を適用して消費税を申告してしまう、という事態が起こり得ます。
これも当然、後から税務調査などで指摘されれば、修正申告と追徴課税の対象となります。
このように売上高の正しい把握は、納税義務の有無だけでなく、有利な特例が使えるかどうかを左右する、二重に重要な意味を持っているのです。
相殺した金額で売上計上すると、納税額を誤る理由
相殺を前提とした売上計上は、2割特例や簡易課税を利用する際の納税額を、過少に計算させてしまう原因となります。
これらの制度は、実際の経費の額ではなく、相殺する前の課税売上高を基準にして納める消費税額を計算する、という共通点があります。
先の例で考えてみましょう。
正しい売上1,100,000円(消費税100,000円)で2割特例を適用すれば、納税額は売上消費税の2割である20,000円(100,000円×0.2)です。
しかし、これを相殺後の88,000円(消費税8,000円)を売上として計算してしまうと、納税額は1,600円(8,000円×0.2)となり、本来の納税額より著しく少なくなってしまいます。
所得の計算上は利益が変わらなくても、消費税の計算においては、基準となる「売上高」そのものが非常に重要です。
この違いを理解していないと、知らず知らずのうちに納税額を誤り、後から修正申告や追徴課税といった事態を招きかねません。
相殺されても正しく処理!総額計上の具体的手順
では、どうすればこのようなリスクを防げるのでしょうか。
答えは、取引が発生した時点で売上と経費を計上する「発生主義」の考え方を取り入れることです。
お金の実際の入出金(入金額)を基準にするのではなく、商品やサービスを提供したという「取引の事実」に基づいて経理処理を行うことで、相殺の有無にかかわらず、売上計上は常に総額で行われるようになります。
具体的なステップは以下の通りです。
- 仕事が完了した時(売上が確定した時)
商品の引渡しやサービス提供が完了したタイミングで、 売上を「売掛金」として全額計上します。
(借方)売掛金 110,000円 / (貸方)売上 110,000円 - 材料購入時
取引先から材料を購入した時点で計上します。
(借方)仕入高 22,000円 / (貸方)買掛金 22,000円 - 入金があった時
材料費が相殺されて入金されたら、以下のように処理します。
(借方)普通預金 88,000円 / (貸方)売掛金 110,000円 (借方)買掛金 22,000円 /
こうすることで、預金通帳の入金額(88,000円)と帳簿が一致し、 かつ売上は110,000円、材料費は22,000円として正しく計上されます。
少し手間に感じるかもしれませんが、この一手間が、将来の大きな税務リスクからあなたを守る最も確実な方法です。
正しい売上計上が、事業を守る第一歩
今回は、意外と見落としがちな相殺を伴う売上計上のリスクについて解説しました。
- 売上と経費は相殺せず、それぞれ総額で計上するのが大原則
- 相殺による売上計上は、消費税の納税義務や納税額の計算を誤らせる原因になる
- 「発生主義」で経理処理を行えば、リスクを防げる
日々の経理で「通帳の入金額=売上」としてしまっている方は、ぜひ一度、ご自身の処理方法を見直してみてください。
もし、この記事を読んで不安に感じたり、具体的な処理方法に迷ったりした場合は、一人で抱え込まず、お近くの税理士にご相談ください。