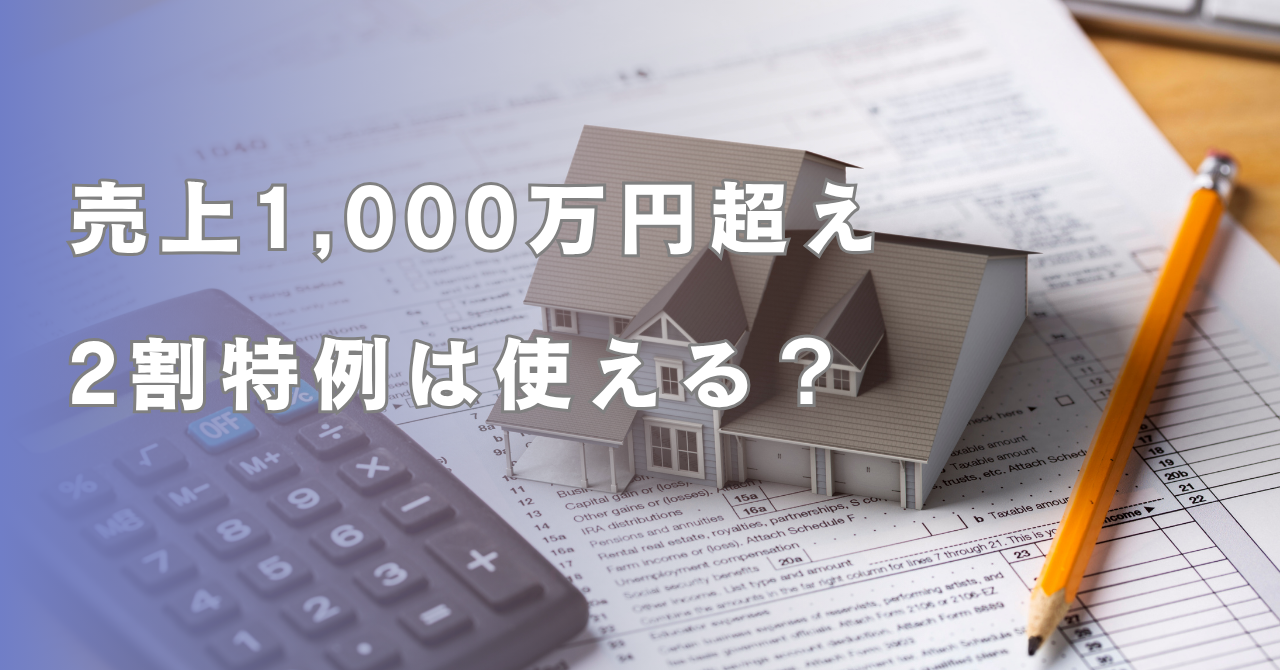消費税のインボイス制度が始まり、多くの事業者さんが対応に頭を悩ませていますよね。
「自分は売上1,000万円を超えたけれど、2割特例は使えるのだろうか?」と疑問を感じている方もいるようです。
この記事では、この疑問に明確に答えつつ、どのような場合に2割特例が使える可能性があるのか、そして売上1,000万円を超える事業者さんがインボイス制度で本当に考えるべきことは何かについて、分かりやすくご説明します。
なお、本記事では制度の全体像を分かりやすくお伝えするため、厳密な用語(課税売上など)を一般的な「売上」と表現するなど、デフォルメして簡略化している箇所があります。
ご自身のケースに当てはまるかどうかの詳細な判断は、ぜひ専門家にご相談ください。
インボイス制度と「1000万超」の売上:そもそも2割特例の対象者とは?
消費税には「免税点制度」というものがあり、これまで多くの個人事業主や中小企業がこの制度の恩恵を受けてきました。
しかし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者さんは、インボイス制度が始まる前から、すでに消費税を納める「課税事業者」でした。
この「課税事業者」か「免税事業者」か、という立ち位置こそが、「2割特例」の対象になるかならないかの最も基本的な分け目になります。
消費税は、日本の消費活動に対して課される税金で、消費者さんが支払った消費税を事業者さんが預かり、まとめて国に納める仕組みです。
このとき、基準期間(個人事業主は前々年、法人の場合は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下の事業者さんは、消費税の納税を免除されていました。これが「免税事業者」です。
つまり、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、この免税点を超えているため、インボイス制度の導入とは関係なく、すでに消費税を計算し、申告・納税する義務を負っていたということになります。
これまでも、売上にかかる消費税から仕入れや経費にかかる消費税を差し引いて納税するという、原則的な方法(もしくは簡易課税)で消費税を納めてきたはずです。
そして、「2割特例」は、インボイス制度の導入に伴い「免税事業者から課税事業者になった方」 の事務負担や納税負担を軽減するために設けられた特別な措置です。
そのため、インボイス制度以前から基準期間の課税売上高が1,000万円を超える状態で課税事業者だった方には、この特例は原則として適用されません。
例えば、岐阜市で飲食店を経営されている個人事業主さんがいらっしゃるとします。
これまでの基準期間の課税売上高が1,000万円を超える状態だったため、インボイス制度が始まる前から課税事業者として消費税を納めていました。
インボイス制度が始まったからといって、この方の消費税の納税義務が新たに発生するわけではありませんし、消費税の計算方法が根本的に変わるわけでもありません。
したがって、原則として「2割特例」を適用することはできないのです。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者さんは、すでに課税事業者であるという大前提を理解することが重要です。
インボイス制度は、主にこれまで免税事業者だった方々に影響を与える側面が大きいため、すでに課税事業者である皆さんは、制度の根幹で立ち位置が変わるわけではない、とまず認識しておきましょう。
この点をご理解いただけると、次の「2割特例」が使える可能性がある例外ケースや、逆に使えないケースの話もすんなり入ってくるかと思います。
注目される「2割特例」は誰のためのもの?1000万超の事業者でも使える例外ケース、そして注意点
売上1,000万円を超える事業者さんで「2割特例」に期待されている方もいるかもしれませんが、この特例はインボイス制度をきっかけに、これまで免税事業者だった方が課税事業者になった場合に適用できる、時限的な納税負担軽減措置です。なお適用期間は、インボイス制度が始まった令和5年10月1日を含む課税期間から、令和8年9月30日を含む課税期間に限られます。
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える状態で既に課税事業者である場合は、この特例は使えません。
しかし、過去に免税事業者だった時期があり、その後売上が1,000万円を超えて課税事業者となった場合でも、一定期間に限り「2割特例」を使えるケースがあります。
消費税の納税義務の判定には基準期間の課税売上高が用いられますが、インボイス制度の開始に伴い適格請求書発行事業者として登録した場合は、基準期間の売上に関わらず課税事業者となります。
本来は基準期間の課税売上などで判定した場合に免税事業者だったところ、この「インボイス登録による課税事業者」となっていた場合に、2割特例の適用対象となります。
また一方で、売上が1,000万円以下で免税事業者だった方がインボイス登録をする際に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった場合など、適用できない課税期間も存在します。
このように、「免税事業者からインボイス登録をした」というだけでは自動的に2割特例が適用されるわけではないため、ご自身の状況を正しく把握しておくことが非常に大切です。
例えば、次のような状況を考えてみましょう。
- 貴事業が令和4年(2022年)の売上が1,000万円以下で、免税事業者だったとします。
- 令和5年(2023年)10月1日のインボイス制度開始を機に、インボイス発行事業者として登録し、課税事業者となったとします。この場合、令和5年10月~12月の期間や、続く令和6年(2024年)の課税期間は、2割特例を使える可能性があります。
- もし令和6年(2024年)に、事業が好調で売上が1,000万円を超えることになったとしても、その売上高は令和8年(2026年)の課税期間の納税義務の判断(基準期間である令和6年の売上)に影響します。
- しかし、令和7年(2025年)の課税期間においては、その基準期間となる令和5年(2023年)の売上が1,000万円以下(免税事業者であったため)であることに基づき、引き続き2割特例を使える可能性があります。
これは、基準期間の売上と、実際に2割特例を適用する期間がずれるために生じる、一時的なズレです。
「売上1,000万円を超えるようになったから、もう使えない」と諦めてしまうのは、もったいないかもしれません。
一方で、もし令和5年10月1日より前に、既に「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者になっていた場合など、適用できない場合も存在します。
このあたりは、非常に複雑な判断が求められることがあります。
したがって、原則として「基準期間の課税売上高が1,000万円を超える」状態で元々課税事業者だった皆さんは、この「2割特例」を使えるわけではありません。
しかし、過去に免税事業者であった期間があり、インボイス制度を機に課税事業者となった場合は、その後売上が1,000万円を超えても、一定期間は2割特例が使える可能性があります。
その一方で、売上が1,000万円以下だった方でも、インボイス登録時の手続などによって適用できないケースもあることを知っておくことが大切です。
これはご自身の状況を細かく確認する必要がある、非常に複雑な判断となります。
売上1,000万円を超える事業者がインボイス制度で本当に確認すべきこと
「2割特例は原則使えないが、一部使える可能性もある」と分かったところで、売上1,000万円を超える課税事業者である皆さんが、インボイス制度で「何もやることがない」というわけではありません。
むしろ、今後の事業に影響を与える重要なポイントがいくつかありますので、しっかり確認しておきましょう。
インボイス制度は、消費税の仕入れ税額控除の仕組みを変えるものです。
これまで、取引先から受け取った請求書が必ずしも適格請求書でなくても、一定の要件を満たせば仕入れ税額控除は可能でした。
しかし、インボイス制度開始後は、原則として適格請求書(インボイス)を保存しないと仕入れ税額控除ができません。
これは、ご自身の仕入れだけでなく、ご自身が発行する請求書にも関わってきます。
適格請求書発行事業者として登録している皆さんは、取引先から求められた際に、適格請求書を正しく発行する義務があるのです。
また、複雑な消費税の計算方法(原則課税や簡易課税)を正しく適用し、税務調査にも対応できるような帳簿付けや証拠書類の管理は、これまで以上に重要になっています。
例えば、貴社がとある部品メーカーから商品を仕入れているとします。
インボイス制度が始まった今、その部品メーカーが適格請求書発行事業者でなければ、貴社はその仕入れに係る消費税を、原則として仕入れ税額控除できなくなる可能性があります。
これは、貴社の消費税納税額が増える可能性を意味しますから、仕入れ先のインボイス対応状況も確認しておきたいところです。(簡易課税や2割特例の場合は関係ありません)
また、貴社自身が適格請求書発行事業者として登録している場合、お客様からインボイスの発行を求められた際に、きちんと要件を満たしたインボイスを発行する必要があります。
請求書の様式を見直したり、経理システムをアップデートしたりといった対応が求められることもあるでしょう。電子帳簿保存法への対応も、一緒に進めていく必要がありますね。
売上1,000万円を超える事業者にとって、「2割特例」は原則直接使えるわけではありませんが、ご自身の状況によっては適用できる可能性があるため、ご自身の過去の納税状況を一度振り返ってみることをおすすめします。
そして、それ以上にインボイス制度は、仕入れ先や販売先との取引関係、そしてご自身の経理業務に大きな影響を与える可能性があります。
- 仕入れ先のインボイス対応状況の確認と、それに伴う影響の把握
- ご自身が発行する請求書のインボイス対応と、適切な発行方法の徹底
- 電子帳簿保存法への対応を含む、経理業務の適正化
これらの点をしっかり確認し、準備を進めることが重要です。
消費税の計算やインボイス制度、電子帳簿保存法は、事業者さんの状況によって最適な対応が異なります。
特に、本記事で触れた「2割特例」の適用可否や、日々の「売上」が「課税売上」に該当するかどうかなど、厳密な判断は専門知識が必要となります。
ご自身のケースで疑問やご不安なことがございましたら、是非専門家までご相談ください。
当事務所では岐阜市をはじめとした個人事業主さんや中小企業の皆さんが、インボイス制度の波を乗り越え、安心して事業に専念できるよう、親身にサポートさせていただきます。