
基礎控除の引き上げで手取り増?2025年12月より影響
税のこと

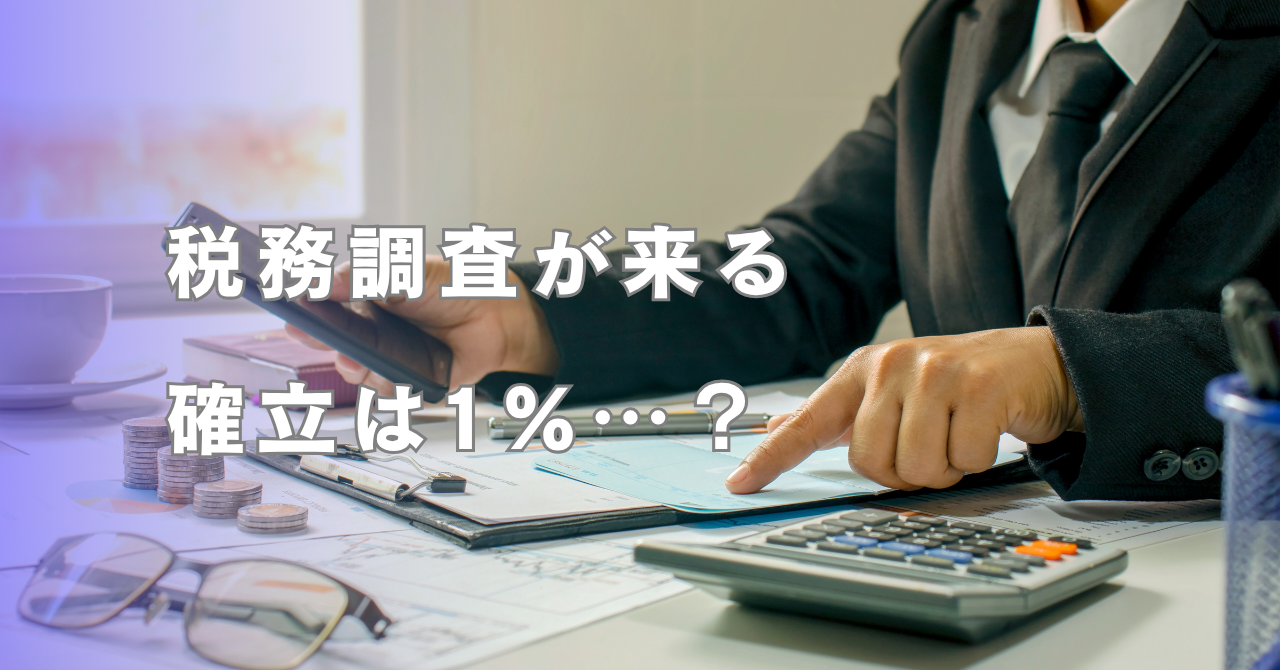
「税務調査が自分のところに来たらどうしよう…」 事業を営んでいる方であれば、一度はこんな不安が頭をよぎったことがあるかもしれません。
税務調査の確率は、おおよそ1%前後と言われています。しかし、この数字だけを見て「自分は大丈夫」と安心してしまうのは、少し早いかもしれません。
Contents
一般的に税務調査の確率は約1%前後(100人に1人)と言われることもありますが、これはコロナ禍前の水準も踏まえた数字です。
最新の公式データ(令和4年分)で見てみると、確率は約0.7%、つまり約140人に1人となっています。
これはコロナ禍で調査件数が一時的に減少した影響も考えられ、今後、調査活動が活発化すれば、確率はまた1%程度の水準に戻っていく可能性も否定できません。
しかし、ここで最も重要なのは、確率の数字が0.7%であれ1%であれ、調査が決してランダム(無作為)に行われているわけではないという点です。
税務署は、限られた人員と時間の中で調査を行うため、膨大な申告データの中から、「何らかの誤りや問題がある可能性が高い」と判断される申告書を優先的にチェックするはずです。
ですから、「確率が低いから大丈夫」と考えるのではなく、「自分は調査対象として選ばれやすい申告をしていないだろうか?」という視点を持つことが、何よりも大切になります。
2024.7月現在では令和5年(2023年)の税務調査の実施データが無いため、令和4年データが最新となります。
・令和4年度の実地調査(所得税の調査)の件数:4.6万件
・令和4年度に確定申告した人数:653.3万人
この数字を使って計算してみます。
4.6万件(実地調査件数)÷653.3万人(申告納税者数)✕100=0.7041…→【0.7%】
※数字は国税庁の資料より
では、具体的にどのような申告書が税務署の目に留まりやすいのでしょうか。
調査対象に選ばれる可能性が高まりそうな代表的な5つのサインをご紹介します。
言うまでもありませんが、無申告は最も調査に繋がりやすい危険な状態です。
税務署は取引先の申告内容など様々な情報網を持っています。
ペナルティも重くなりますので、必ず期限内に申告を行いましょう。
売上が毎年900万円台で推移している場合も、注意深く見られる傾向があります。
課税売上高1,000万円が消費税の納税義務の境目となるため、「納税を避けるために、売上を過少に申고しているのではないか」という視点で見られるリスクが高まります。
これは正しく申告していても実際に900万円台であれば致し方ないところがありますが、規模的にも税理士に依頼する事を検討されても良いのではないでしょうか。
売上や利益、経費の金額が前年と比べて大きく変動している場合、その「理由」に注目されます。
もちろん、事業が成長すれば数字は動くもの。
大切なのは、その変動の理由を客観的に説明できることです。
青色申告で提出する貸借対照表も、重要なチェックポイントです。
特に、「現金」勘定がマイナスになっているケースは少なくありません。
これは会計ソフトの不具合ではなく、入力ミスや売上計上漏れが原因です。
この状態は会計の基本ルールから外れており、申告内容全体の信頼性を損ないます。
飲食店などの現金商売は、取引記録が追いづらいという特性上、売上管理がより重要視されます。
また、国税庁が公表する「申告漏れ所得金額が高額な業種」(近年では経営コンサルタントやブリーダーなど)は、必然的に税務署の視線も厳しくなる傾向にあります。
・経営コンサルタント
・くず金卸売業
・ブリーダー
令和元年~令和2年くらいまでは風俗、キャバクラ・キャバレーがしばらく1位、2位を占めていましたが、令和2年~3年ぐらいから変わってきました。
コロナの影響が大きい事が予想されますね。
税務調査に怯えるのではなく、「いつ調査があっても問題ない状態」を普段から作っておくことが大切です。そのための具体的な対策を3つご紹介します。
結論として、日々の取引を正しく記録し、その根拠となる資料を整理しておくことが最大の防御策です。
調査は無作為(ランダム)に選ばれるわけではないため、確率の数字に一喜一憂するのではなく、ご自身の申告内容そのものに目を向けることが重要です。
上記のような点は、税務調査の対象として選ばれる一因となり得ます。
日々の取引を正しく記録し、根拠となる資料を整理・保存することが、結果として最善の税務調査対策となります。
この記事が、ご自身の申告内容を見直すきっかけとなれば幸いです。
税務調査が来やすい時期については過去の記事を参照ください。
免責事項